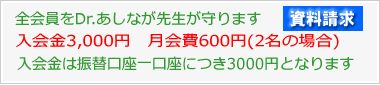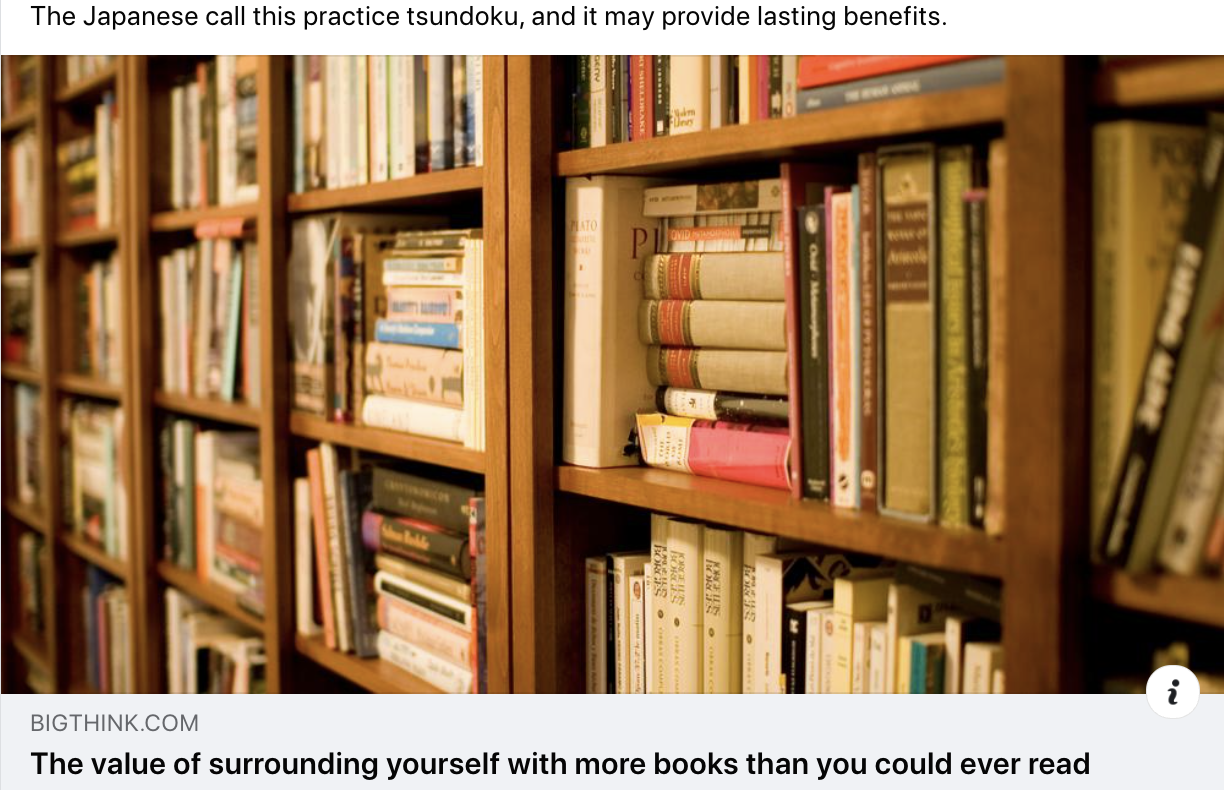 購入するなどして手に入れた書籍を読む事なく、自宅で積んだままにしている状態を意味する「積ん読/積読」。日本には遅くとも明治時代から存在する言葉ですが、近年はBBCやCNN、ニューヨーク・タイムズ紙など、海外の大手メディアでも続々と取り上げられた事により、そのままTsundokuで通じる国際語になりつつあります。基本的にはユーモアに富んだ言葉として紹介されていましたが、アメリカのネットメディア「Big Think」は、その効能に迫った特集記事を配信しています。記事は、統計学者のナシーム・ニコラス・タレブ氏の、「読まずに積んだ状態にされた本は、 まだ知らない物事があるという事を、 常に思い出させてくれる」存在であるという指摘を紹介。また、本の所有と読書は密接に関係している、という過去の研究結果も取り上げられており、それによると、多くの蔵書がある家庭で育った子どもは、大人になってから識字能力、計算能力、情報通信技術能力が向上したそうです。さらに、編集者ジェシカ・スティルマン氏の、「あなたが読んでいない本は全て、 あなたが無知である事の表れです。 しかし、自分がどれほど無知であるかを知っていれば、 多くの人々より遥かに先にいるのです」という言葉を紹介。そして最後に、「読まなくては」と思わせてくれる事自体が、積ん読の価値だという一文で記事はまとめられています。積ん読に罪悪感を覚える人はかなり多いようで、この記事に救われる外国人が続出していました。「最高のランキングだ!」 英紙選出『日本を知る為の本トップ10』が話題に…
購入するなどして手に入れた書籍を読む事なく、自宅で積んだままにしている状態を意味する「積ん読/積読」。日本には遅くとも明治時代から存在する言葉ですが、近年はBBCやCNN、ニューヨーク・タイムズ紙など、海外の大手メディアでも続々と取り上げられた事により、そのままTsundokuで通じる国際語になりつつあります。基本的にはユーモアに富んだ言葉として紹介されていましたが、アメリカのネットメディア「Big Think」は、その効能に迫った特集記事を配信しています。記事は、統計学者のナシーム・ニコラス・タレブ氏の、「読まずに積んだ状態にされた本は、 まだ知らない物事があるという事を、 常に思い出させてくれる」存在であるという指摘を紹介。また、本の所有と読書は密接に関係している、という過去の研究結果も取り上げられており、それによると、多くの蔵書がある家庭で育った子どもは、大人になってから識字能力、計算能力、情報通信技術能力が向上したそうです。さらに、編集者ジェシカ・スティルマン氏の、「あなたが読んでいない本は全て、 あなたが無知である事の表れです。 しかし、自分がどれほど無知であるかを知っていれば、 多くの人々より遥かに先にいるのです」という言葉を紹介。そして最後に、「読まなくては」と思わせてくれる事自体が、積ん読の価値だという一文で記事はまとめられています。積ん読に罪悪感を覚える人はかなり多いようで、この記事に救われる外国人が続出していました。「最高のランキングだ!」 英紙選出『日本を知る為の本トップ10』が話題に… このサイトの記事を見る
このサイトの記事を見る
海外「日本の概念に救われた!」 国際語となった『積ん読』の驚くべき効能に外国人が歓喜
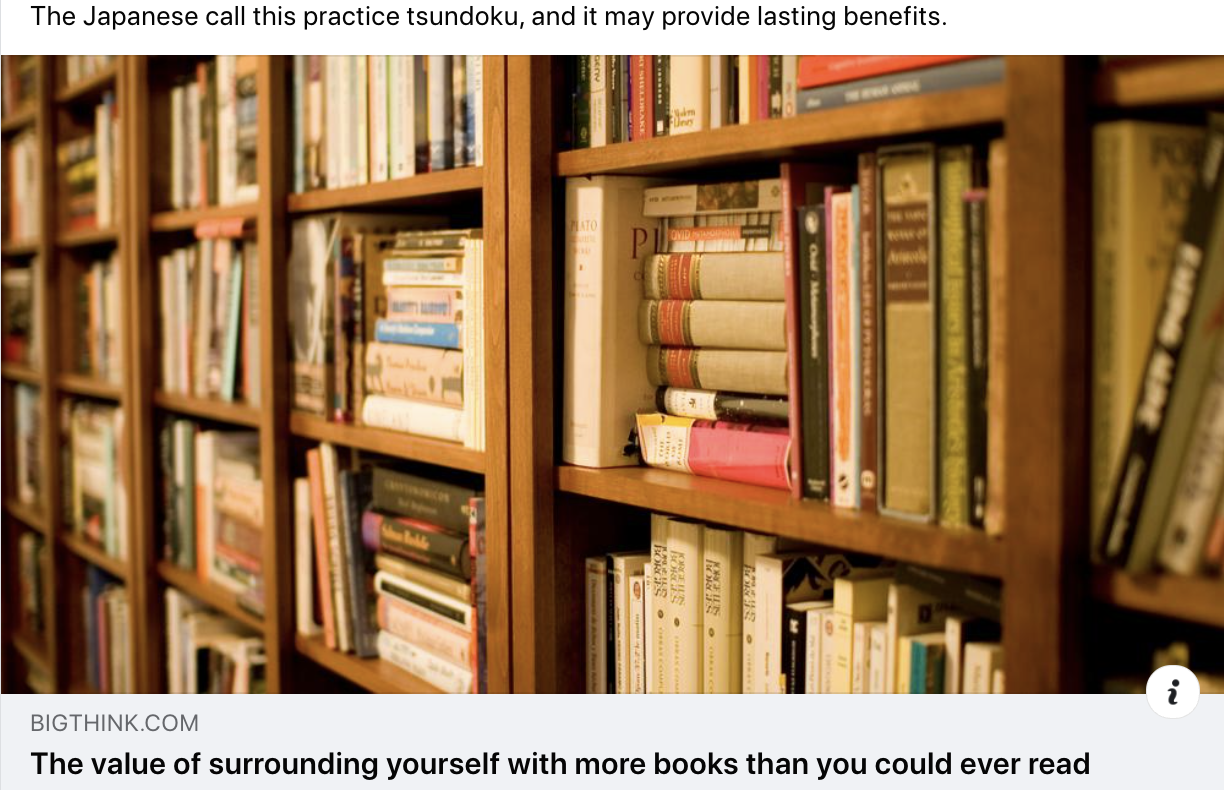 【海外の反応】 パンドラの憂鬱
【海外の反応】 パンドラの憂鬱